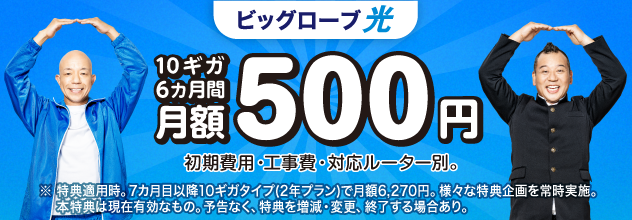HAPSという言葉を聞いたことはあるでしょうか?
近年サービスが開始される、通信系のプラットフォームである……など、断片的な情報だけはご存知の方もいるかもしれませんが、詳しくはわからないのではないでしょうか。
HAPS(ハップス)は簡単にいえば、空を飛ぶ基地局です。モバイル回線の電波は、地上にある基地局を介して通信する仕組みですが、2026年からは上空からの通信サービスの提供が予定されており、そのシステムがHAPSです。
どのようにしてサービスが提供されるのか、何ができるようになるのでしょうか。本記事ではHAPSについて、特徴やメリット、期待されている用途などを解説していきます。
目次
HAPSとは
HAPS(ハップス)とは、基地局としての機能を搭載した無人航空機を成層圏に飛ばして、通信サービスを提供するシステムです。一度打ち上げたら、数週間から数ヶ月程度上空で稼働し続けます。燃料電池やソーラーパネルなどを搭載しており、稼働中もエネルギーが補給される仕組みです。
HAPSに搭載されている基地局では、地上に設置されているモバイル回線の基地局と同じ4Gや5Gなどの電波を扱います。そのため、スマホやモバイルルーターなどの通信に使用可能です。
現在ではまだ実証実験の段階ですが、NTTドコモが2026年にHAPSの商用化を予定しているほか、ソフトバンクも2017年から技術開発を進めています。
成層圏はどんな環境か
そんなHAPSが稼働する成層圏とはどんなところでしょうか。
成層圏とは地上10kmから50kmくらいまでの範囲にある空気の層です。我々が生活している空間は対流圏という空気の層で、成層圏は対流圏よりも一段階上にあります。
成層圏は雲があるところよりも上に位置しているため、常に晴れている環境です。雨が降ることがないため、常にソーラーパネルで充電できます。
また、対流圏との境目付近は気温が非常に低く、高度が上がるにつれて気温も高くなっていきます。HAPSは成層圏の中でも地上から20km前後のところを飛行します。気温は-50度程度で空気密度は地上の20分の1程度という環境です。空気抵抗が少ないため、エネルギー消費も少なく済むというわけです。
HAPSの特徴・メリット
現状では地上に設置されている基地局と通信衛星を利用して通信が行われています。基地局はスマホなどでのモバイル通信で利用されている通信インフラです。通信衛星は船舶や航空機、衛星電話などでの通信に利用されています。HAPSはこれら両方の用途での利用が予定されているものです。
では、HAPSが実用化されると、地上に設置された基地局や通信衛星を利用する場合と比べてどのようなメリットがあるのか見ていきましょう。
1台での通信カバーエリアが広い
従来の地上の基地局の場合、1台のカバーエリアは、半径数kmから数十km程度にとどまります。これに対して、HAPSなら1台のカバーエリアが半径100km程度と広いのが特徴です。HAPSが実用化されれば、地上の基地局だけだとカバーエリア外になってしまう場所でも、スマホを使えるようになるでしょう。
通信遅延が少ない
通信衛星を利用する場合と比べて、通信遅延が少ないのもHAPSのメリットです。通信衛星の場合には、地上から2,000kmも離れたところにあるため、どうしても遅延が生じてしまいます。その点、HAPSなら地上からの距離は20km程度のため、通信衛星と比べればかなり近い距離であり、通信遅延が少なくなります
着陸時にメンテナンスができる
通信衛星の場合にはいったん打ち上げたら10年程度は戻って来ることはありません。これに対して、HAPSは打ち上げ後、数週間から数ヶ月経過すれば地上に着陸します。そのたびにメンテナンスができるのがメリットです。不具合箇所がないかどうかをチェックしたり、新しい技術を取り込んだりできます。
HAPSのデメリット
HAPSを商用化するまでには、プロトタイプを作り、試験飛行するなどして、試行錯誤を繰り返さなければなりません。多額の開発費用がかかるのはデメリットといえるでしょう。商用化した後にも、機体のメンテナンスにコストがかかります。
また、HAPSは太陽光をメインのエネルギー源として動く仕組みです。高緯度地域では冬場の日照時間が少ないため、夏場しか使用できません。
HAPSの実用化により期待されている用途
HAPSが実用化されれば、さまざまな用途に活用できます。HAPSの実用化で期待されている用途の例を見ていきましょう。

山間部や離島などでのスマホの利用
地上の基地局だけだと山間部や離島などをカバーするのは難しいため、現状、スマホを使えないエリアもあります。その点、HAPSなら上空からサービスを提供し、通信カバーエリアも広いことから、山間部や離島などもカバーできるようになります。HAPSが実用化されれば日本国内でスマホが使えない場所はほとんどなくなると考えられます。
ドローンへの活用
上空から電波を送受信するため、ドローンとの相性も良好です。通信が安定するため、これまでよりもドローンの活用の幅が広がるでしょう。
IoTへの活用
IoT(Internet of Things)は家電製品などを中心にあらゆるものをインターネットに接続することですが、この分野への活用も期待できます。HAPSが実用化されれば、インターネットに接続できない場所がほぼなくなり、山間部や離島を含めどこでも、IoTを実現できると考えられます。
災害時の通信インフラの確保
地上の基地局は、大地震や台風などの自然災害の被害を受けると、正常に稼働できなくなってしまうこともあるでしょう。その点、成層圏にあるHAPSなら、自然災害の影響を受けません。地上の通信インフラが使用できなくなっても、HAPSを利用すればインターネットに接続できます。災害時の通信インフラとしての活用が期待できるでしょう。
まとめ
HAPSは成層圏に無人航空機を打ち上げて提供するモバイル回線の通信サービスです。地上の基地局と比べてカバーエリアが広く、通信衛星と比べて遅延が少ないなどのメリットがあります。定期的に着陸するためメンテナンスも可能です。
2026年に商用化が予定されており、ドローンや災害時の通信インフラなど活用できる用途は多いです。山間部や離島などでの活用も期待されています。HAPSの実用化でより便利な世の中になっていくでしょう。







 T.A
T.A