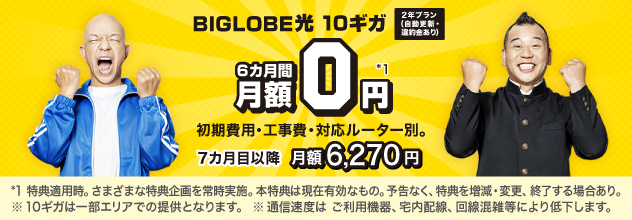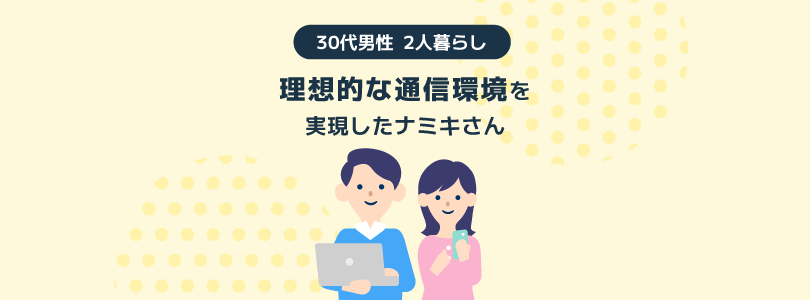光回線を使用していて十分な速度が出ていても、ファイルを送受信する際に時間がかかることがないでしょうか。その場合には伝送帯域が狭いのかもしれません。
大容量の通信をスムーズに行うためには通信速度だけでなく伝送帯域も必要です。本記事では、伝送帯域について、通信における役割や通信速度との違いを解説していきます。
目次
通信速度とは

通信速度とは、データを送受信する際のスピードを表すものです。通信速度の数値が高ければ、データを高速で送受信できます。
交通に例えると、車が走行するときのスピードと捉えていいでしょう。
伝送帯域とは
伝送帯域とは、一度に送信できるデータ量を表すものです。伝送帯域が広ければ、一度に多くのデータ量を送受信できます。
交通に例えると、道路の広さと捉えられます。道路が広ければ、一度に多くの車が通れるというわけです。
伝送帯域が狭いとどうなるのか
つまり、伝送帯域が狭いというのは、一度に送受信できるデータ量が少ないことを意味しています。伝送帯域が狭いと通信速度が速くてもスムーズな通信はできません。道路が狭くて渋滞していて、車がスピードを出したくても出せないような状態です。
送受信するデータ量が少ない場合には、伝送帯域が狭くてもさほど影響はありません。しかし、大容量のデータを送受信する際には、普段よりも速度が落ちて時間がかかってしまいます。
伝送帯域はLANケーブルで決まる

伝送帯域の狭さが問題になるのは、主にLANケーブルでPCを有線接続している場合です。使用しているLANケーブルのスペックにより伝送帯域が決まります。
LANケーブルはCATで分類されている
LANケーブルはCAT(カテゴリー)で分類されています。CATにより最大通信速度と伝送帯域が決まる仕組みです。
「CAT5」や「CAT6」のように数字が付いていますが、数字が大きいほどスペックが高いことを意味しています。
一般的な光回線では、CAT5eかCAT6、CAT6Aのどれかが使用されているケースが多いです。稀にCAT5のLANケーブルを使用しているケースもあります。
具体的なスペックは次のとおりです。
・CAT5 :100Mbps、100MHz
・CAT5e:1Gbps、100MHz
・CAT6 (※ケーブルの長さが55mより長い) :1Gbps 、250MHz
・CAT6 (※ケーブルの長さが55m以下) :10Gbps 、250MHz
・CAT6A:10Gbps 、500MHz
CAT6AのLANケーブルなら伝送帯域が広いため快適に通信できます。
また、CAT7以上のLANケーブルもありますが、コネクタの形状が異なり、一般家庭用ではありません。
▶【徹底解説】10Gbps(10ギガ)LANケーブルとは?選び方から種類、活用方法まで
CATの確認方法
LANケーブルのCATはパッケージに記載されていますが、開けたらすぐに捨ててしまうでしょう。パッケージが手元にない場合には、LANケーブルそのものの印字を見て確認できます。
「CAT6」のように、カテゴリー名がそのまま印字されていることもあるため確認してみましょう。
そのまま印字されていない場合には、「ANSI/TIA」で始まる文字列の印字があることが多いです。カテゴリー名を意味しているものであり、具体的には次のように対応しています。
・CAT5 :ANSI/TIA/EIA-568-B.1
・CAT5e:ANSI/TIA/EIA-568-B.2
・CAT6 :ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1
・CAT6A:ANSI/TIA-568-B.2-10
まとめ
伝送帯域は一度に通信できるデータ量を示す数値で、回線速度はデータを送受信するスピードを示す数値です。大容量のデータを快適に送受信するためには、回線速度が速いだけでなく伝送帯域も広くなければなりません。
伝送帯域は使用しているLANケーブルで決まります。LANケーブルを確認し、カテゴリーが低いようであれば、CAT6Aのものに買い替えるのがおすすめです。






 T.A
T.A