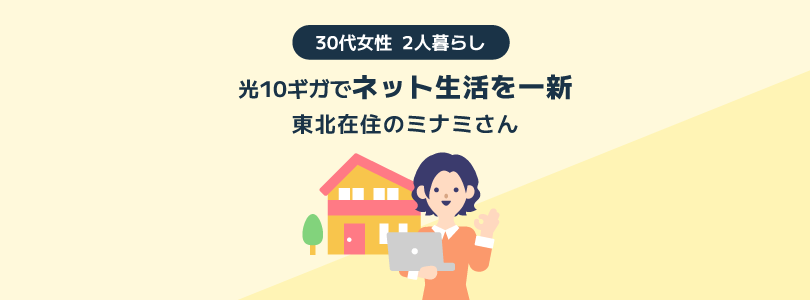同じ10ギガ回線でも端末によって通信速度に違いが出る?徹底検証!-05


渡辺まりか
- 本記事は作成時点の内容です。
最近話題の光回線10ギガタイプ(BIGLOBE提供)を、IT系ライターが実際に契約するところからやってみた体験談を綴るシリーズです。
モニターのお話をいただき、BIGLOBE光10ギガ回線の開通から、1カ月が経過しました。筆者はライティングをなりわいにしています。仕事で使うのは主にPCで、まれに2020年発売の「iPad Pro 12.9-inch (第4世代)」(A12Z Bionicチップ)や2023年発売の「Amazon Fire Max 11」、「Lenovo 14e Chromebook Gen3」などを使うこともあります。
気分や環境によって端末を変えて作業できるのは、執筆環境をオンラインに限定しているからです。「オンラインに限定」というのはどういうことかというと、本体に保存するメモ帳アプリやMicrosoft Wordソフトなどを使うのではなく(といっても、最近のMicrosoft Wordは、クラウドドライブのOneDriveに保存されるのが規定値になっていますが)、Webアプリの「Google Document」を使っているということです。
取材などでは、高性能カメラを搭載したスマートフォンで撮影し、いったんGoogle フォトにアップロードします。そこからダウンロードして使ったり、納品先(仕事の依頼先)によっては、Google フォトからそのままGoogle Documentに写真を挿入したりして、写真を活用します。
光回線を10ギガにしたことで、これらの作業が断然速くなったな、と感じているのですが、本当に速くなっているのでしょうか。ただのプラシーボ効果ではないのでしょうか。また、端末によってアップロードやダウンロードに差が出るのでしょうか。
気になったので検証することにしました。
検証環境をチェック
10ギガ回線をWi-Fiを使って家中で使えるようにしてくれる無線LANルーターは「TP-Link Deco BE85」で、原稿執筆時点で販売中の無線LANルーターでは最新のWi-Fi 7規格に準拠した製品です。Wi-Fi 7では6.0GHzの周波数帯を利用するためデータ通信が高速で良いのですが、一方で通信距離が短く、壁などの障害物に弱いというデメリットもあります。
筆者は別のプロバイダの1ギガ回線も併用しており、こちらは「E-WMTA2.4」を無線LANルーターとして使っています。Wi-Fi 6規格に対応しており、周波数帯は2.4GHzと5GHz。Wi-Fi 6の最大通信速度は9.6Gbpsですが、対応しているのは最大 2.4Gbpsです。以下に環境をまとめました。
| BIGLOBE光 10ギガの検証環境 | 他社1ギガ光回線の検証環境 | |
|---|---|---|
| 無線LANルーター | TP-Link Deco BE85 | E-WMTA2.4 |
| 対応Wi-Fi規格 | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6 |
| 対応周波数帯 | 2.4GHz帯/5GHz帯/6GHz帯 | 2.4GHz帯/5GHz帯 |
| 伝送速度 | 22Gbps*1 | 最大2.4Gbps |
- 複数の周波数帯(6GHz、5GHz、2.4GHz)を同時に利用した際の数値です。理論上の最大値であり、実際の転送速度を示すものではありません。接続する機器の仕様やネットワークの混雑状況、電波の状態などにより速度は低下します。
そして、今回テストに利用するのは以下の端末です。
| 機種名 | OS | CPUまたはSoC | Wi-Fi規格 | 発売年 |
|---|---|---|---|---|
| Steam Deck OLED | Steam OS | AMD Custom APU 0932 | Wi-Fi 6E | 2023 |
| AYANEO Pocket S | Android 13 | Snapdragon G3x Gen2 | Wi-Fi 7 | 2024 |
| iPhone 16 | iOS 18.5 | A18 | Wi-Fi 7 | 2024 |
| Lenovo 14e Chromebook Gen 3 | Chrome OS | intel N200 | Wi-Fi 6E | 2023 |
| AYANEO Pocket MICRO | Android 13 | Media Tek Helio G99 | Wi-Fi 5 | 2024 |
端末によって通信速度に違いはあるのか?
さて、OSも発売年もCPUも異なるさまざまな端末で通信速度のテストをしてみましたが、実際に端末によって違いは出てくるのでしょうか。
仕事で、写真や動画をアップロードする作業が頻繁に生じるので、今回はそれにちなみ、「約1GBの動画をGoogleドライブにアップロードする」というテストを行いました。
| 機種名 | Wi-Fi規格 | 10ギガ回線 | 1ギガ回線 |
|---|---|---|---|
| Steam Deck OLED | Wi-Fi 6E | 1:38’12” | 1:47’73” |
| AYANEO Pocket S | Wi-Fi 7 | 27’12” | 1:05’73” |
| iPhone 16 | Wi-Fi 7 | 31’55” | 57’17” |
| Lenovo 14e Chromebook Gen 3 | Wi-Fi 6E | 33’18” | 56’92” |
| AYANEO Pocket MICRO | Wi-Fi 5 | 37’35” | 1:33’80” |
結果は上記の通りです。こうして比較してみると、「通信速度は端末の性能によって異なる」ということがわかりました。
また、意外だったのは、非力なCPUを搭載しているはずのLenovo 14e Chromebook Gen3や、Wi-Fi 5対応のAYANEO Pocket MICROが健闘しているということでした。
10ギガ回線と1ギガ回線の比較
なお、当たり前ですが、1ギガ回線でのデータ通信速度はどの端末でも、10ギガ回線より遅くなりました。
AYANEO Pocket Sは2台ともストレージ容量以外、全く同じスペックなので、2台並べてアップロードとダウンロードの検証動画を撮影しました。ダウンロード時に、10ギガ回線と接続している下側の端末でワンテンポ、操作が遅れてしまいましたが、本動画のそれぞれダウンロード開始のタイミングをチェックしてかかった時間を計測したところ、10ギガ回線では33秒11、1ギガ回線では46秒19という結果になりました。
33秒という時間は、人によって感じ方が異なるかもしれませんが、筆者にとっては「あっという間」でした。アップロードボタンをタップ(またはクリック)してからドリンクを手に取り、キャップを開けて一口飲んでから元に戻している間に終わるようなイメージです。
10ギガ回線の恩恵にあずかるには端末も新しいほうが良い
今回の検証の結果、搭載しているCPUやSoC、Wi-Fi規格の新しさに関係なく、端末の個性により、通信できるスピードに違いが生じてしまうということがわかりました。
スマートフォンでは良い結果が、PCではそれなりの結果となり、特にSteamDeck OLEDはアップロードが得意ではないということもわかりました。
また、スピードテストで良い結果が出たとしても、実務では必ずしもそれが反映されるわけではないことも実証されたといえます。

▲こちらはSteamDeck OLEDのWebブラウザでスピードテストを行った結果。アップロードで660.5Mbpsという速度が出ていても、1GBのデータのアップロードに、1分以上の時間がかかってしまいました
新しく、さらに性能の良い端末のほうが、10ギガ回線の恩恵に充分にあずかれますが、もちろん、Wi-Fi 5以上の規格に対応している端末であれば、1ギガ回線より10ギガ回線のほうが速いのも確かです。
時間帯や周囲の状況などにより、結果は異なるので、必ずしもすべての場合に同じ結果が出るわけではないということも承知おきいただけると幸いです。

Contributor 渡辺まりか